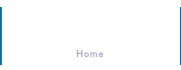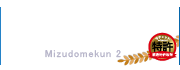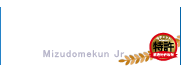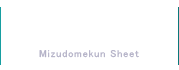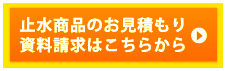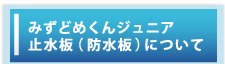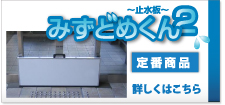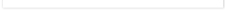- トップ>
- 止水板のみずどめくんジュニア>
- どんな所に施工可能?
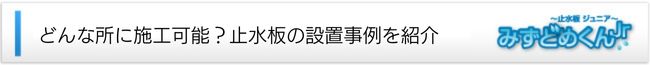 どんな所に施工可能?
どんな所に施工可能?
止水板の設置事例を紹介
止水板(防潮板)施工例1 片開扉編 (両側に止水パッキンのあたり代が有る場合)
 片開自動扉金物設置後
片開自動扉金物設置後 片開自動扉止水板(防潮板)設置後
片開自動扉止水板(防潮板)設置後
設計の段階からの案件だったので、
止水板(防潮板)の止水パッキンのあたり代を作って頂きました。
止水板(防潮板)施工例2 片開扉編 (片側にパッキンのあたり代が無い場合)
 片開扉部止水板設置後
片開扉部止水板設置後 脱着式サイド柱での止水板(防潮板)設置状況
脱着式サイド柱での止水板(防潮板)設置状況 脱着式サイド柱用ステイ(常時設置)
脱着式サイド柱用ステイ(常時設置)
既存の建物だったので、止水板(防潮板)パッキンのあたり代が有りませんでした。
お施主様より、有効開口を狭くしたくないとの事だったので、
脱着式サイド柱(ステイ常設)タイプを納めさせて頂きました。
止水板(防潮板)施工例3 床面平滑処理(インターロッキング編)
 設置個所の床面がインターロッキング仕上げになっています。
設置個所の床面がインターロッキング仕上げになっています。
モルタル仕上げや金物設置で平滑処理を行う事もありますが、
今回は、御影石(バーナー仕上げ)で、平滑処理を行う事になりました。
どの様な手順で施工するのかを御覧いただきたいと思います。 止水板(防潮板)設置個所周辺のインターロッキングを撤去します。
止水板(防潮板)設置個所周辺のインターロッキングを撤去します。 インターロックング撤去個所の躯体側(基礎部分)に
インターロックング撤去個所の躯体側(基礎部分)に
塗布防水用の下地処理剤を塗布します。 下地処理剤の上から、塗布防水を行います。
下地処理剤の上から、塗布防水を行います。
上の写真の白い部分が、塗布防水の色(茶色)になっています。 バサモルの上に床面平滑用の御影石を仮置きして、
バサモルの上に床面平滑用の御影石を仮置きして、
インターロッキングと御影石の高さや目地幅を確認します。 御影石を一度外して、ゆるめのモルタルをバサモルの上に流します。
御影石を一度外して、ゆるめのモルタルをバサモルの上に流します。 再度、御影石を設置個所にゆっくり下ろして、御影石の高さと目地幅を調整します。
再度、御影石を設置個所にゆっくり下ろして、御影石の高さと目地幅を調整します。
調整後、インターロッキングと接する部分に石目地を打設します。 石目地押しの作業
石目地押しの作業 石目地乾燥後、建具枠と接する部分にシールコーキングを行い、
石目地乾燥後、建具枠と接する部分にシールコーキングを行い、
床面の平滑処理は終了です。 シールコーキング後
シールコーキング後 自動扉の方立に止水板(防潮板)固定用ピンアダプターを設置して
自動扉の方立に止水板(防潮板)固定用ピンアダプターを設置して
設置工事は終了です。 止水板(防潮板)の設置状況
止水板(防潮板)の設置状況
止水板(防潮板)施工例4 床面平滑処理(幅が狭い石目地編)
 設置個所の床面が石貼り仕上げになっています。
設置個所の床面が石貼り仕上げになっています。
床が石貼りの場合、タイル貼りに比べれば、非常に良い平滑度になっていますので、
石目地のみの平滑処理で平滑化は終了です。
通常、石目地幅が大きい場合、弊社では、電動ディスクグラインダーにタイルカット用の
ダイヤモンドホイールを用いて、平滑化の為に既存目地の撤去を行い、石の表面に合わせて
石目地を再打設します。
今回の施工例は、石目地幅が2mm程しかない為、電動ディスクグラインダーと
ダイヤモンドホイール(ホイール厚1.1mm~1.4mm)を使用した場合、
万が一にも既存の石に傷を付けてしまうかもしれません。
その様な石目地の幅が狭い場合、どんな手順で施工するのかを御覧いただきたいと思います。
石目地は、結局、オルファカッターで地道に深くなるように作業をしました。
目地の深さを3mm程になった所で、目地の再打設です。
 今回の様に、幅2mm程の目地では、通常の石目地材を再打設しても、目地の奥まで目地材を
今回の様に、幅2mm程の目地では、通常の石目地材を再打設しても、目地の奥まで目地材を
詰め込む事が困難なので、エポキシパテを使用しました。 パテのみの色では、既存目地色とは異なってしまうので、色調整も行います。
パテのみの色では、既存目地色とは異なってしまうので、色調整も行います。
(ケース内の左下の緑色っぽい物がパテです) 石目地の平滑処理後
石目地の平滑処理後 シールコーキング作業前に、止水板(防潮板)設置状況確認を行い、
シールコーキング作業前に、止水板(防潮板)設置状況確認を行い、
シールコーキングで作業終了です。
みずどめくんJr